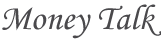株式投資AIツールとロボアドの比較
違いその1:「手数料」か「AI利用料」か
ロボアドは永久に費用がかかる
ロボアドには年率1.1%(税込)くらいの手数料が発生します。これは、預けている「総資産」に対する1.1%です。利益に対する1.1%ではありません。例えば1000万円預けている場合、たとえ損失を出していたとしても、年間11万円を支払わなければなりません。この負担は大きいです。
運用手数料がない
一方、銘柄抽出AIの場合、ソフト利用代が発生します。運用手数料はかかりません。AIのおかげで運用資産がいくら膨らんでも、それに連動してコストが増えることはありません。
ただし、ソフト利用代は、資産の大小に関係なく数万円以上します。
手元資金が20~30万円しかない人は、手が出ないでしょう。
違いその2:「ETF」か「個別銘柄」か
ロボアドは、ETF(上場投資信託)が主な投資対象です。ETFとは、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などの指数と連動する投資信託です。つまり投資スタイルとしては、いわゆる「パッシブ運用」になります。積極的に多くのリターンを求めるというよりは、消極的に稼ごうとする姿勢です。
ロボアドは自分の「暴走」を阻止するのが目的
ETF投資は、わざわざロボアドを介さなくても、誰でも簡単にできます。したがって、そもそもロボアドを利用すること自体、あまり大きな意味はないといえます。 むしろ一時的な感情やフェイク情報に振り回されて無謀な投資をしないための「歯止め」という意義のほうが大きいです。
アクティブ運用
これに対して、銘柄抽出AIは、個別の銘柄を買うために使われます。AIが銘柄をピックアップし、その情報に基づいて、投資家が自分自身で買うか買わないか、買う場合はいつどれだけ買うのか、を判断します。株価指数を上回る成果を狙う「アクティブ運用」となります。
複雑な組み合わせができるロボアドもある
ただ、ロボアドの中にも、 SBI系列の「フォリオ(FOLIO)」のように、 海外の債券など様々な投資信託を組み合わせるような高度で複雑な投資を行っている事例もあります。 こうした高度なロボアドは、ETFだけに投資する商品に比べて価値が高いといえるでしょう。
違いその3:歴史的な背景
ロボアドの場合
ノーベル経済学者の理論
ロボアドには、米国の経済学者ハリー・マーコビッツ氏が唱えた「現代ポートフォリオ理論」が用いられています。
この理論は、1つの銘柄に集中投資するのは損失リスクが高い、というのが骨子です。マーコビッツ氏は、複数の銘柄に加え、債券や不動産など異なる金融商品に分散投資した方が、もうかる期待値が同じであれば損失のリスクが下がることを理論化しました。
この理論は、最適な資産配分を実現するための基礎的な考え方となりました。マーコビッツ氏はこの理論で1990年ノーベル経済学賞を受賞しています。
リーマンショック後のアメリカで普及
ロボアドはまずアメリカで普及しました。きっかけとなったのは2008年のリーマン・ショックでした。
リーマンショックによる株価大暴落で、多数の人たちが大きな損失を出しました。リスクが高いアクティブ運用を避けて安定性を求めるパッシブ運用への支持が高まりました。そのタイミングで、ロボアドによる安定的な運用サービスを提供するベンチャー企業が続々と登場しました。
日本では「ウェルスナビ」がけん引役に
日本でロボアドが本格的に普及し始めたのは2016年ごろです。
2016年2月に資産運用サービスを手掛ける「お金のデザイン」(東京)がTHEO(テオ)という名称でロボアドを活用したサービスを開始しました。さらに2016年7月には「ウェルスナビ」が立ち上がりました。
マネックスも参入
2016年9月には「マネックス・アセットマネジメント」(当時:マネックス・セゾン・バンガード投資顧問、東京)が同様のサービスをスタートさせました。
東証に上場
このうち、運用実績や使い勝手の良さなどが評価されたウェルスナビが大きな伸びを見せました。ウェルスナビは2020年(令和2年)に東証マザーズに株式を上場しました。
大きなチャンスを逃す
ところが、ロボアドは「リスクを減らす」という発想を最優先しているため、大きなチャンスがめぐってきたときに、それに見合う利益を出すのは困難であることが、徐々に明らかになりました。
「物足りない」との口コミが拡大
それが決定的になったのが、2023年上半期の日本株の上昇局面です。ウォーレン・バフェットの「日本買い」をきっかけに、海外投資家が日本株に殺到。日経平均株価が急騰し、バブル後の高値を更新しました。このとき、ロボアドは波に乗り遅れ、十分な運用成績を出すことはできませんでした。外国人投資家においしいところを持っていかれました。その結果、日本の個人投資家の間で「ロボアドは物足りない」という口コミや評判が定着することになりました。
AI銘柄抽出ソフトの場合
コンピューターの自動売買システム
一方、AI銘柄抽出ソフトは当初、ヘッジファンドや機関投資家の間で普及しました。
これら機関投資家のシステムでは、コンピュータが特定の論理やルールに従って自動的に注文を行います。「アルゴリズム取引」とも呼ばれます。
基本的なシステムは、以下の機能を備えています。
- (1)利用アルゴリズム(売買論理)の種類を選択できる。
- (2)各種パラメーター(取引条件)を設定できる。
- (3)自らの注文で株価が大きく変動するマーケット・インパクトを抑制しながら売買を実行する。例えば、大口注文を複数の小口注文に細分化するなど。
割安株を探し出す
銘柄抽出AIの開発には、多数の数学者やコンピューター科学者が参加しました。その結果、性能が飛躍的に発達し、膨大な情報分析を短時間で処理することが可能となりました。チャート分析や業績などに基づいて割安株を探し出すことも可能になりました。
個人に開放
ただ、これらのAIは高価であるため、個人投資家には手が出ませんでした。ところが、2021年ごろから一般個人にも提供されるようになりました。「オープンソースAIフレームワーク」と呼ばれる技術の進歩によって、高性能なAIが低コストで作られるようになったためです。

AI投資の注意点
先端AIは過去の株式市場のデータやパターンを分析したうえで、統計モデルや機械学習アルゴリズムに基づき、将来の価格変動を予測することができます。大量のデータを高速で処理し、市場のトレンドやパターンを検出することを得意としています。
このため、先端AIのアドバイスは、株投資の参考情報や意思決定のサポートとして役立つことが多いです。また、特定の戦略や条件に基づいて株式の選択やポートフォリオの最適化を支援することもできます。
完璧な予測は不可能
ただし、株式投資は、ご自身の運用目標やリスク許容度に合わせて行われるべきです。AIが提供するアドバイスはあくまで参考情報であり、取引の最終的な決定は投資家が自ら行わなければなりません。
株式市場には予測不能な要素や不確実性がつきまといます。高性能なAIであっても、完璧な予測や確実なアドバイスを提供することは不可能だということです。